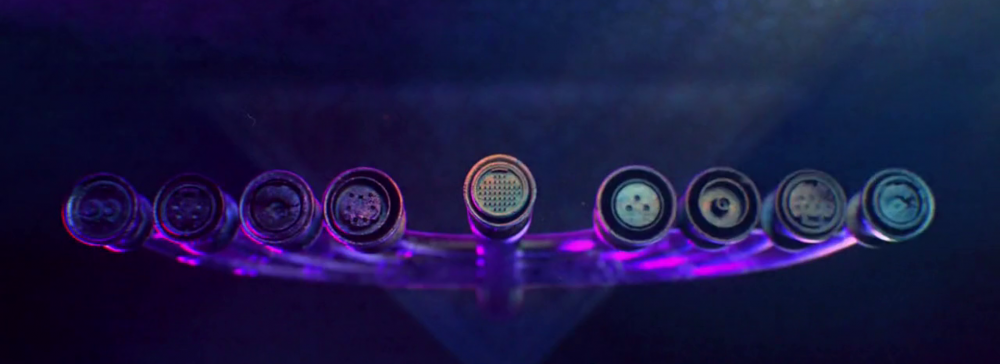日本にきて一年間は東京外語大のJLCで日本語学んだ。その一年間の最後に、日本語で卒業論文を書かなあかんかった。ちょうど今自分のをみつけたから、そのままで載せる。
1. はじめに
「以前のこと、わたし荘周は夢の中で胡蝶となった。喜々として胡蝶になりきっていた。自分でも楽しくて心ゆくばかり にひらひらと舞っていた。荘周であることは全く念頭になかった。はっと目が覚めると、これはしたり、荘周ではないか。ところで、荘周である私が夢の中で胡 蝶となったのか、自分は実は胡蝶であって、いま夢を見て荘周となっているのか、いずれが本当か私にはわからない。荘周と胡蝶とには確かに、形の上では区別 があるはずだ。しかし主体としての自分には変わりは無く、これが物の変化というものである。」
現実は何かという質問は以上の荘子の夢の隠喩でたぶん最初に問われた。荘子は、戦国時代の中国で活動し、百家争鳴の時代の多数の思想家の一人であった。そのとき以来のどの時代の哲学者にとっ ても、世界の実存の問題は哲学のもっとも面白い分野であった。世界と現実の定義、その二つの違いはそもそもそんなに明白だといえない。辞書によって言葉の意味の説明は得られるが、その哲学的な意味は簡単ではない。まず、言葉の定義を挙げ、論文全体ではその哲学的な意味を考察する。
2. 知識可能性
「世界」というのは、我々人間の活動する物理的空間を意味し、存在するものの実 際の状態を言う。「現実」を定義することができるが、その定義された現実について何が知られているだろうか。正確に言えば、確実な知識が獲得できるだろうか。そう考えれば、世界の中で住んでいるすべての意識のある生き物は、感覚されている現実について何らかの知識を持っている。問題は一つしかない。それは「感覚」である。外界の情報を獲得する方法は、現在のところ、全部五感を通る。五感の働きについての情報も例外ではない。つまり、五感の働きについて確実な知識を得ない限り、感覚によって外界からの情報がどのように変化されるか、わからないので、外界の性質についてのすべての情報を疑問に思うべきである。この論法の重要性を、フランスの哲学者デカルトの有名な「我思う、ゆえに我あり」ということばはよくあらわしている。
しかし、確実な知識の獲得の問題は哲学だけの問題ではない。ただし、文化の歴史の中で、哲学だけが返答を試みてきた。科学は、説明したい現実の中でこのような抽象的な問題に答えを出すことはめったになかった。しかし、十九世紀から二十世紀にかけておける科学革命で、それはだいぶ変わった。量子力学は世界の基本的な作用を検討する際、この問題 にぶつかった。その結果、原爆研究などで有名な、ドイツのハイゼンバークは不確定性の原理を発表した。その原理により、ある二つの物理量の組み合わ せにおいて、二つとも正確に測定できない。つまり、二つの物理量の一方は測定値の標準偏差を小さくすればするほど、他方の標準偏差が大きくなるので ある。その理由は、簡単に言えば、科学の測定方法である。ある粒子の性質を測定するために、ほかの粒子との反作用を観測するので、その反作用は粒子の性質をどのように変えたか、わからない。即ち、科学の測定機械は五感と同様に、確定されたものの状態を変える可能性がある。つまり、我々人間は科学的方法でも世界の実存について完全に確実な知識を獲得できないのである。
また、問題になることは、測定機械と感覚器だけではない。もし、感覚と測定によって獲得される情報が変わらないとしても、その情報によって起こされた、精神の中の写像は誰でも同じか。だれにとっても、「赤」という色は同じ心的写像を起こすのか、わからない。
つまり、上記からわかるように、外部については具体的な知識を獲得できない。しかし、「現実」がこのような関係であれば、何が本当に存在するか。別の言い方をすれば、我々の感覚されるものの中で、実際に存在するものは何か。
3. いろいろな哲学
3-1. 独我論
「独我論」の「独」は「だけ」、「我」は「私」を意味し、独我論で実際に存在するものは、独我論を考える者の精神だけである。荘子の夢を例とすれば、問題は荘子の正体だけでなく、世界の正体も同様である。つまり荘子は胡蝶になったことだけでなく、世界全体も夢見る。また、荘子の精神しか存在せず、それ以外は全部荘子の夢である。独我論は、信奉者があまりいない。それには理由が多くある。まず、各人にとっては、自分の意識だけを正確に知っているため、誰でも独我論の「世界」である可能性があり、哲学の存在論や認識論にとって意味がなくなる。また、あまり世界の見方も変えない。独我論を信じても、他人や世界全体は想像の産物でしかないので、他人に教えるのは意味がない。また、実際に存在するものは我精神だけであっても、世界を制御するのは無意識であり、無意識については心外のものと同様に確実な知識がない。つまり、無意識は意識の見地から見れば、外界と同じなので、「我」から独自の現実が存在する。
また、哲学自体を考えれば、目的は何であろうか。哲学者にとって、現実は見える世界より複雑である多くの場合を考えることである。しかし独我論は哲学の終点で、完了したもので、もう考えることがないので、哲学者にとって面白さがなくなり、ほかの分野に進むべきである。
3-2. 他人も存在する場合
私の論理にとって、次は世界全体が現実であるという論ではなく、それよりもまず他の精神の存在を仮定する論である。それを「共精論」とし、「独我論」と反対になる。感覚される世界は我精神の産物でなく、それどころか精神のあるもの全部の「貢献」の総体である。
共精論は、唯物的な世界がない。その感覚は実際に他の心、他の精神との接触の結果である。世界を構成する精神は神経回路のように接続し、互いに感じる。その感じは世界の感覚である。ただし、感じた他の精神は世界の中でどのように表されているか、わからないので、日本の神道やほかの汎神論も可能性がある。
独我論と同様に、共精論でも世界の変化の問題が出てくる。世界は精神の産物であれば、それを制御できるはずである。世界は精神にとって共同的なイメージがある。そのイメージ、即ち感覚される現実を変えるのは、他の精神に影響を与え、その共同的イメージを変えるのである。しかし全人類や宇宙人たち(いるとしたら)の精神の共同的イメージを変えるためには非常な努力が必要である。つまり、個人として世界を変えられないのは、他心の「惰力」のせいであるといえる。また、我精神以外の精神も存在するので、その精神にこの世界の中で共精論を教えれば、協力で世界を変え、もっと良い所にすることができるであろう。十分の精神に十分の影響を与えれば、ハロー・キティーを実際に道を歩くものにする可能性がある。その上、共精論により他の世界もありうる。空想科学もののパラレル・ワールドとも言えるが、実際に我々の世界の精神集合に接触しない他の精神集合である。他の世界と接触すればどうなるかは、それを構成する精神集合の性質によって違い、想像もできない。
共精論は完璧だということにはならない。まず、目標は世界と現実を説明することによってそれらの働きを明らかにすることであろう。しかし、こういう目標は達成しない。世界の動きを説明する今日知られている物理的法則のほかに、世界の実際の働きを説明するために、その働きは多数の精神の活動なので、まだよくわからない心理学の法則も必要とする。また、サルトルにより、人間を定義できない。即ち、人の定義を作れば、その人は自分の変化、進化によりその定義を無効にする。ただし、この定義をなくす能力は自由である。それで、共精論の世界を説明するために、それを構成する精神を定義するべきなので、世界の認識を人間の自由が制限する。
さらに、共精論はオッカムの剃刀という、科学にとって基本的な格言にも反対である。オッカムの剃刀により、「必要なく多数性を仮定してはならぬ」、つまり理論をできるだけ簡単にするものである。しかし共精論は哲学的にミニマリストの独我論ほども、科学的にミニマリストの実在論ほども簡単ではない。
3-3. 実在論
実在論というのは、言葉に対応するものは、それ自体存在するという立場である。実在論には、中世の観念実在論や科学的実在論などの分野があるが、本論で紹介するのは素朴実在論である。
素朴実在論は、認識論の常識的な分野である。世界は常識の通りある。常識というのは、社会の構成員が持っている、当たり前のものとされている価値観、知識や判断力のことである。このように、物体は物質に構成され、認識に関係なく存在し、大きさ、色、形、模様などの性質を実際に持っている上、我々はその性質を正確に認識できる。しかし、その以外に何の存在も仮定しないという考えである。
素朴実在論は、一番簡単な理論である。ただし、問題が多くある。まず、素朴実在論の認識論上の立場は素朴過ぎる。感覚されているものはいつもその実際に存在すると言うと、錯覚や幻覚の問題が出てくる。錯覚とは、感覚器が実際と異なる知識を得る現象である。感覚器に誤りがあることは事実である。よく使われている例として、黄疸という病気の症状によって全部がより黄色に見えることがある。しかし認識論に限らず、他の科学にも批評されている。その中の一番重要なは、量子力学からの批評であろう。量子力学により、粒子に測定により変わらない性質がなさそうであり、素朴実在論はそれらが存在するように言う。
このように、素朴実在論は一つの点以外に常識に過ぎない。その一つの点は、素朴実在論は哲学の方法を利用し議論する。
4. 終わりに
素朴実在論はこの考え方の終点でもないし、上記で紹介された学派が認識論の全体であるという訳でもない。この論文の目的は、どの哲学の専門家でない人のための解説と同様に、哲学的な思考を鼓舞するものである。内容も、構造もそのために注意深く計画された。哲学の概観は歴史的の見地から取り扱うことが多いが、関心を引き起こし、じっくり考えてもらうために、一般に退屈に思われている歴史からもっと離れた、理論的流れで進むことにした。このように読解だけで、読者は哲学の考え方に慣れて、計画の目的を記すことによって、読者にその考え方に慣れたと自覚させることができるとおもう。
「哲学」を意味する西洋の言葉はギリシア語、φιλοσοφία(フィロソフィア)から来、文字通りの意味は知(σοφία)が好き(φίλος)だということである。それを忘れず、皆自分の立場や意見を考えることにより、世界や社会のことを注意深く見るようになり、それでこの世の中でよりよく暮らすことができる。
<参考文献>
- Bertrand Russell(1946、2004)『History of western philosophy』Routledge Classics
- Wikipedia